Essay エッセイ
さくらとこころ
第1章|旅立ちと東京の印象 ― 桜の下で見た日本(1970年代)

五十年以上前、まだ若かった私は、世界を知る旅に出ようと決めた。 そして、その最初の国として日本を選んだ。 お金はほとんどなく、分別も今思えばほとんどなかった。 「いちばん遠い国から始めれば、もし途中でお金が尽きても、帰るための方法を探すしかないだろう」――そんな無鉄砲な理屈であった。
当時としては天文学的な金額だった一万九千ドラクマを払い、私はKLMの飛行機に乗り込んだ。 ベイルート、ニューデリー、バンコク、マニラと、乗客の乗り降りを繰り返しながら、二日後の真夜中、ようやく東京に着いた。 入国審査では苦労した。片道切符しかなく、宿の住所もなく、所持金も十分ではなかったからだ。 それでも、同じ飛行機に乗っていたギリシャ船員たちと共に“ギリシャ的創造力”を発揮し、審査官をどうにか説得した。 結局、私は無事に入国を許され、胸を躍らせながら案内所へ向かった。 紹介されたホテルに泊まってみると、そこは一泊で一か月分の予算を吹き飛ばすほどの高級宿。 こうして、最初の教訓を得た――「値段は必ず先に聞くこと」。

東京の第一印象は、圧倒的な人の波だった。 どこを見ても小柄な人々が群れをなし、まるでひとりの母親が何千人もの子を産んだかのように、みなよく似ていた。 それでも、街全体が活気に満ち、何か新しいものへ向かって動き出している空気があった。
そして、私の記憶にいまも鮮やかに残るのは――桜だ。 桃色の衣をまとい、街中を染め上げるように咲き誇っていた。 公園は桜色の海のようで、夜になると、灯籠を飾った小舟が水の道をゆったりと進んでいた。 桜の花びらが風に舞い、静かに川面を流れていく。 その光景の中で、私は「遠い国に来た」という実感を初めて深く味わった。

当時の東京の人々は、ほとんどが黒や紺のスーツ、あるいは着物姿。 西洋ではミニスカートやベルボトム、長髪が流行していた時代に、ここでは統一された規律と控えめな上品さがあった。 私はというと、栗色の金髪(当時はまだ白くなっていなかった)に青い瞳、背も高く、まるで異世界の生き物のように目立っていた。 子どもたちは興味津々で後をついてきたり、母親の後ろに隠れたり。 私はまるでサーカスから逃げ出した見世物のような気分だった。

有限会社ノスティミア
A. Fragkis
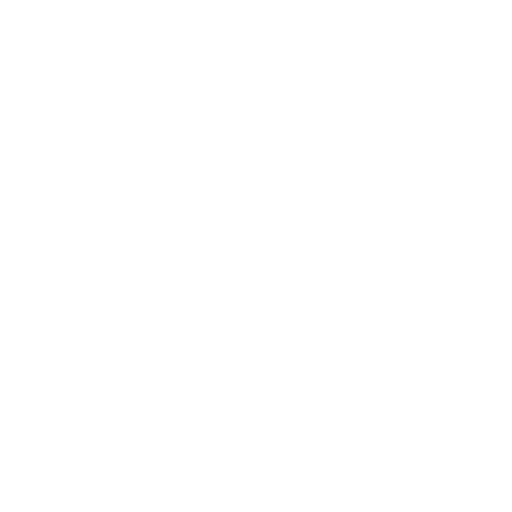
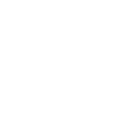



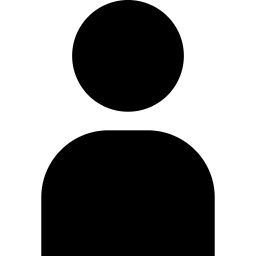










 ギリシャを訪ねたとき
ギリシャを訪ねたとき