Essay エッセイ
さくらとこころ
第7章|桜の下に残した心 ― 日本という“もう一つのふるさと”
教師としての日々は静かに過ぎていった。
授業を終えた午後には、子どもたちと笑いながら遊び、
春になると海沿いの道を歩き、満開の桜の下で立ち止まった。
日本の人々はみな誠実で、礼儀正しく、
控えめでありながら、温かな思いやりを持っていた。
戦後からまだ25年。
1970年代の日本は、豊かさの入り口に立ちながらも、
人と人との間に“こころ”が確かに存在していた時代だった。
金銭よりも信頼、便利さよりも人情。
一杯の酒、一皿の焼き鳥を分け合いながら笑い合う。
私は、そんな日本人の姿に心を打たれた。
次第にこの国は、私にとって“もう一つのふるさと”となっていった。
春。
また桜が咲いた。
風に舞う花びらの中で、私は静かに誓った。
――「いつか必ず、この国に戻ってくる。」
それは若気の感傷ではなく、
確かに自分の中に根づいた“何か”への約束だった。
やがて滞在の終わりが訪れ、
私は日本を離れてギリシャへ帰国した。
祖国の光と風を再び感じながらも、
心のどこかで日本の穏やかな笑顔を恋しく思っていた。
年月が流れた。
そして――1994年。
私はイギリスで、ひとりの日本人女性と出会った。
それが、いまの妻である。
その出会いは偶然のようでいて、
まるであの春、桜の下で誓った約束が
時を越えて導いてくれたかのようだった。
イギリスでの生活が始まり、
二人で新しい家庭を築いた。
その中で、再び日本への思いが静かに芽生えていった。
2001年、私たちは家族で日本へ戻った。
そして、かつて心を奪われたこの国で、
ギリシャの太陽と風の恵みを伝えたいと強く思った。
そうして私は、ギリシャ産ワインと食品の輸入を始めた。
それは、若き日の旅の続きであり、
桜の下で交わした“こころの約束”を果たす行いでもあった。
いま、春になるたびに桜を見上げる。
花びらが風に舞うたび、
1970年代のあの日に置いてきた自分の心が、
静かに息づいているように感じる。
Sakura and Kokoro ― 桜と心。
それは、私の人生をつないだ二つの言葉。
ギリシャの光、日本の心。
二つが出会って生まれたものこそ、
いまの私のすべてなのだ


有限会社ノスティミア
A. Fragkis
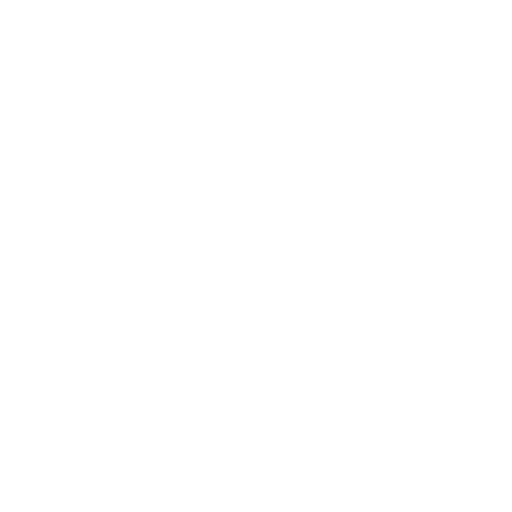
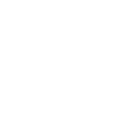



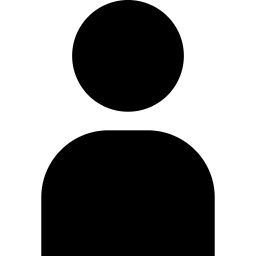










 さくらとこころ
第6章|黒塗りの車の行き先
さくらとこころ
第6章|黒塗りの車の行き先
