Essay エッセイ
さくらとこころ
第6章|黒塗りの車の行き先 ― そして“英語教師”になる
私を乗せた黒塗りの車は、やがて小さな地方都市に入った。
建物の前で車が止まり、運転手は慌てて降りてドアを開け、
深く頭を下げた。
私は促されるまま、広いロビーへ。
そこには制服を着た三人の女性がいて、
一糸乱れぬ動作でお辞儀をしながら「いらっしゃいませ」と唱えた。
彼女たちの笑顔と整然とした所作に、
ようやく私は“悪いことには巻き込まれていない”と確信できた。
昨日の夜の出来事が脳裏をよぎった。
あの酔っぱらいの紳士が、何か関係しているのだろうか?
案内役の女性が、再び丁寧にお辞儀をして私を会議室へと導いた。
部屋には畳敷きではなく、洋式のテーブルと椅子が並んでおり、
すでにお茶のセットが用意されていた。
「すみません」と一言だけ知っている日本語を口にして、
私は差し出された湯飲みを受け取った。
緑茶の味は、正直いえば私の好みではなかった。
しかし、一緒に出された小さな菓子は悪くなかった。

やがて、ドアが静かに開いた。
入ってきたのは――
昨夜の酔っぱらいだった!
「オォ〜〜! アメリカじん!! コンニチワ!!」
私は思わず笑い出した。
すべてが一瞬でつながった。
だが、彼の後ろにはもう一人の男がいた。
背が高く、細身で、赤みがかったブロンド。
柔らかな笑顔で私に手を差し出した。
「マクファーソン」と彼は名乗った。
その英語は――何とも不思議だった。
ドイツ語の抑揚とスコットランド訛りが混ざったような独特の響き。
私は彼に尋ねた。
「Could you speak slowly, please?(ゆっくり話してもらえますか?)」
彼は笑い、ゆっくりと話し始めた。
どうやら私は、I?Hという巨大造船会社の本社にいるらしい。
ここは呉という町で、住民のほとんどがこの会社に勤めているという。
そして――昨夜の酔っぱらいの紳士は、その会社の副社長だったのだ。
「それで、私に何の用が?」と聞くと、
マクファーソンは言った。
「あなたに、英語を教えてもらいたい。」
私は耳を疑った。
当時の私の英語力といえば、語学学校の外を歩いた程度。
とても“教師”を務められるようなものではない。
しかし、彼は笑って続けた。
「心配しないで。彼らは、英語をまったく理解していない。
あなたのほうが、はるかに上だ。」
そう言って彼は肩をすくめ、
「Don’t forget?you’re American. Like me!」と冗談めかして言った。
(どうやら、まだ私を“アメリカ人”だと思っているらしい。)
正式なオファーは、驚くほど丁重な形で提示された。
地元の小学校(会社が運営している)で、
4クラスの子どもたちに英語を教えてほしいというのだ。
給料は、旅人の私には信じられないほど良かった。
「教育経験はないが……」と口ごもる私に、
副社長は満面の笑みで「OK! OK!」を繰り返した。
こうして私は、“英語教師”としての新しい人生を始めることになった。

初日の授業。
教室のドアを開けると、
20人ほどの小さな子どもたちが、
机にきちんと座って私を見上げていた。
年齢は8歳から12歳ほど。
黒髪のつや、真剣なまなざし、そして――無邪気な笑顔。
私は黒板にチョークで「A B C」と書き、
「Good morning!」と声を出した。
子どもたちは一斉に「グッモォニン!」と叫び、
教室が笑いに包まれた。
それが、私の“教師人生”の第一歩だった。
授業のたびに私は前夜、次の日のレッスンを必死に予習した。
時には単語の発音を間違え、
文法の説明でつまずいた。
だが、子どもたちは決して笑わず、
一生懸命に私の言葉をまねしようとした。
「日本の子どもたちは本当に勤勉で、素直だ。」
そう感じるたびに、心の奥が温かくなった。
数か月後、私は十分な給料を手にし、
再び旅を続ける資金を得ていた。
だが、何よりの財産は――
子どもたちの笑顔と、
彼らのまっすぐな心に触れた時間だった。

有限会社ノスティミア
A. Fragkis
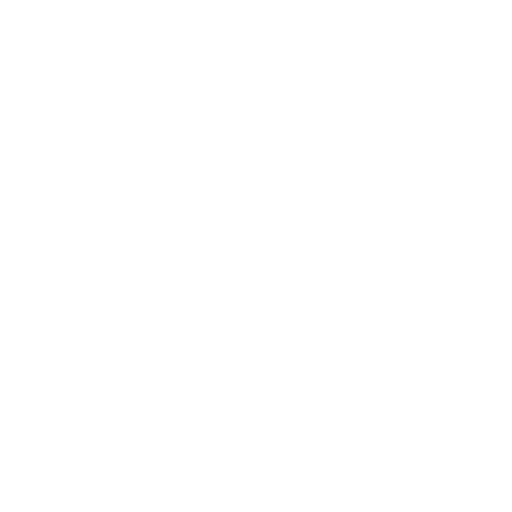
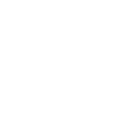



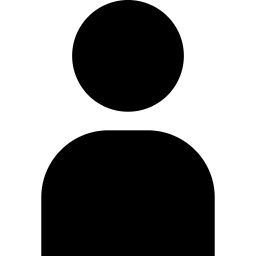










 さくらとこころ
第5章|焼き鳥屋の夜
さくらとこころ
第5章|焼き鳥屋の夜
