Essay エッセイ
さくらとこころ
第5章|焼き鳥屋の夜 ― “アメリカ人ですか?”から始まる奇縁
日々の生活の中で、私は少しずつ東京の街に慣れていった。
どこに行っても人の波。看板の文字は理解できない。
それでも、人々の礼儀正しさと秩序だった暮らしぶりに、
安心感のようなものを覚えるようになっていた。
そんなある晩、私は偶然入った小さな焼き鳥屋で、
一生忘れられない出会いをした。
焼き鳥とは、鶏のさまざまな部位を串に刺して炭火で焼いたものだ。
日本では、庶民的で、安くて美味しい夜の食べ物。
店内は煙がもうもうと立ちこめ、カウンターの向こうでは
職人が忙しそうに串を焼いている。
男たちはスーツ姿のまま、ビールや酒を飲み、
会社の話をしながら笑っていた。

私はカウンターの端に座り、
慣れない箸を手にビールを飲んでいた。
その隣に、小柄でスーツ姿の中年紳士が座っていた。
顔はすでに真っ赤で、明らかに酔っている。
彼は私をちらりと見ると、にやりと笑って言った。
「オォ〜〜〜、アメリカじん、ですか?」
「ノー、ノー」と首を振ったが、彼はまったく意に介さず、
「ア〜、ソウデスカ! アメリカじんデス!」と
嬉しそうに叫んだ。
私は苦笑するしかなかった。
「彼は次に、
「エーゴ、サベテ?」(英語話せるか?)
と聞いてきた。
「YES!」と勢いよく答えると、
彼の目が一瞬輝いた――と思ったら、
「アッ、ソウ! アメリカじんデスネ!」とまた同じ返答。
まったく話が通じない。
それでも彼は上機嫌で話し続けた。
酔っぱらい特有の長広舌で、
私はうなずくしかなかった。
しばらくして、彼は胸ポケットから小さな名刺入れを取り出し、
一枚の名刺を差し出した。
手にはしっかりとした力があり、笑顔には誇りがあった。
私はその美しい活字を眺めたが、もちろん何が書いてあるか読めない。
名刺を受け取る私を見て、彼は満足そうに頷いた。
ところが、彼は私にも名刺を求めているらしい。
私は持っていなかったので、軽く頭を下げて謝った。
すると彼は、何度も同じ質問をしてきた。 「ドコ、スンデマスカ?」 「どこに泊まっているのか?」と尋ねているらしい。 ようやく周囲の客や店員の助けを借りて理解した。

私はポケットから取り出したマッチ箱の中から、
宿泊しているホテルの名前が印刷されたものを選び、彼に見せた。
彼はじっとそれを見つめ、
「ア〜、ワカリマシタ!」と大きくうなずいた。
そのときは、それ以上のことなど想像もしなかった。
酔っぱらいとの偶然の出会いが、
私の旅の行方を大きく変えることになるとは――。
翌朝、いつものように早起きした私は、
8時半ごろに部屋のドアをノックされて驚いた。
朝食を運んでくる女性(日本人女性の年齢は本当にわかりづらい!
15歳にも55歳にも見える)だった。
しかし今日は手にトレイを持っていない。
彼女は満面の笑みを浮かべながら、
何やら日本語で一生懸命に話している。
まったく理解できなかったが、
どうやら「誰かがあなたに会いに来ている」ということらしい。
私は好奇心に駆られて階下のロビーへ降りた。
そこには、黒いスーツの男が一人、きちんと立っていた。
彼は深々とお辞儀をし、名刺を差し出した。
昨夜の酔っぱらいがくれたものと同じ会社のロゴが印刷されていた。
男は英語をほとんど話さなかったが、
「車で来てください」と身振りで示し、
外には黒塗りの車が停まっていた。
運転席には白い手袋をはめた運転手。
1970年代のギリシャでは、黒いスーツと黒塗りの車といえば、
決して“良い知らせ”ではなかった。
私は一瞬、凍りついた。
「まさか昨日の酔っぱらいが何か…?」
「警察? スパイ? それとも――?」
考えれば考えるほど不安は募る。
しかし、ホテルの従業員たちは笑顔で見送ってくれる。
その穏やかな表情に、少しだけ安心し、
私は覚悟を決めて車に乗り込んだ。
車は市街地を抜け、川沿いの道を進んでいった。
車窓の外には田んぼや農家が広がり、
美しい田園風景が流れていく。
だが、私の頭の中は混乱の渦。
「もし本当に逮捕されるのなら、なぜ広島の中心部ではなく、
わざわざ郊外まで?」
「私は何をしたというんだ?」
心臓が早鐘を打った。
やがて車は、とある小さな町の前で止まった。
そこには立派なビルがあり、入口には制服姿の受付嬢が三人。
彼女たちは完璧な笑顔で一斉に頭を下げ、
「いらっしゃいませ!」と声をそろえた。
私はようやく少しだけ、安心した。

有限会社ノスティミア
A. Fragkis
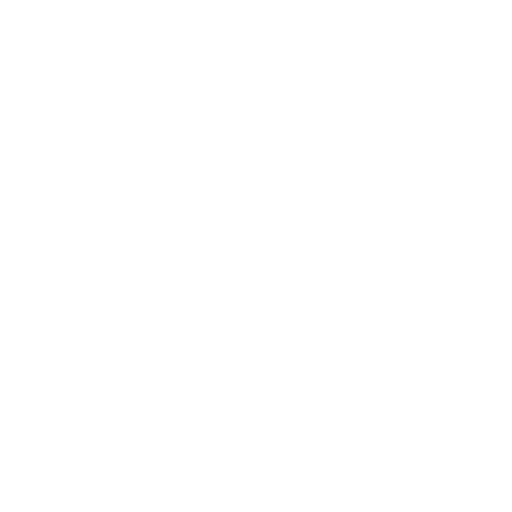
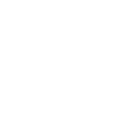



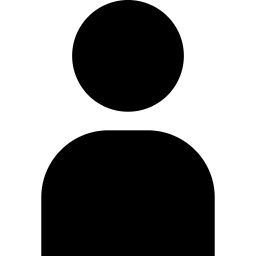










 さくらとこころ
第4章|少女たちとの出会い
さくらとこころ
第4章|少女たちとの出会い
